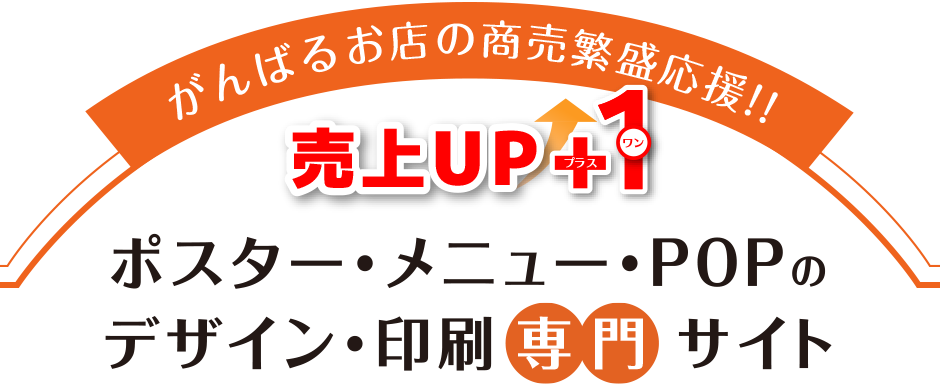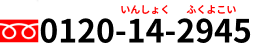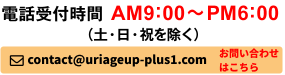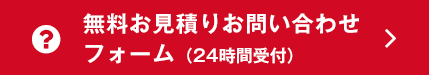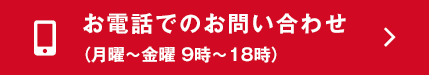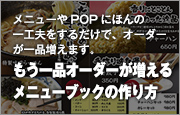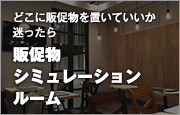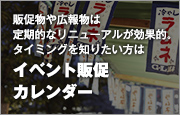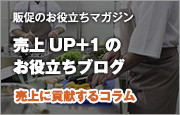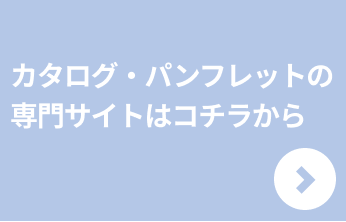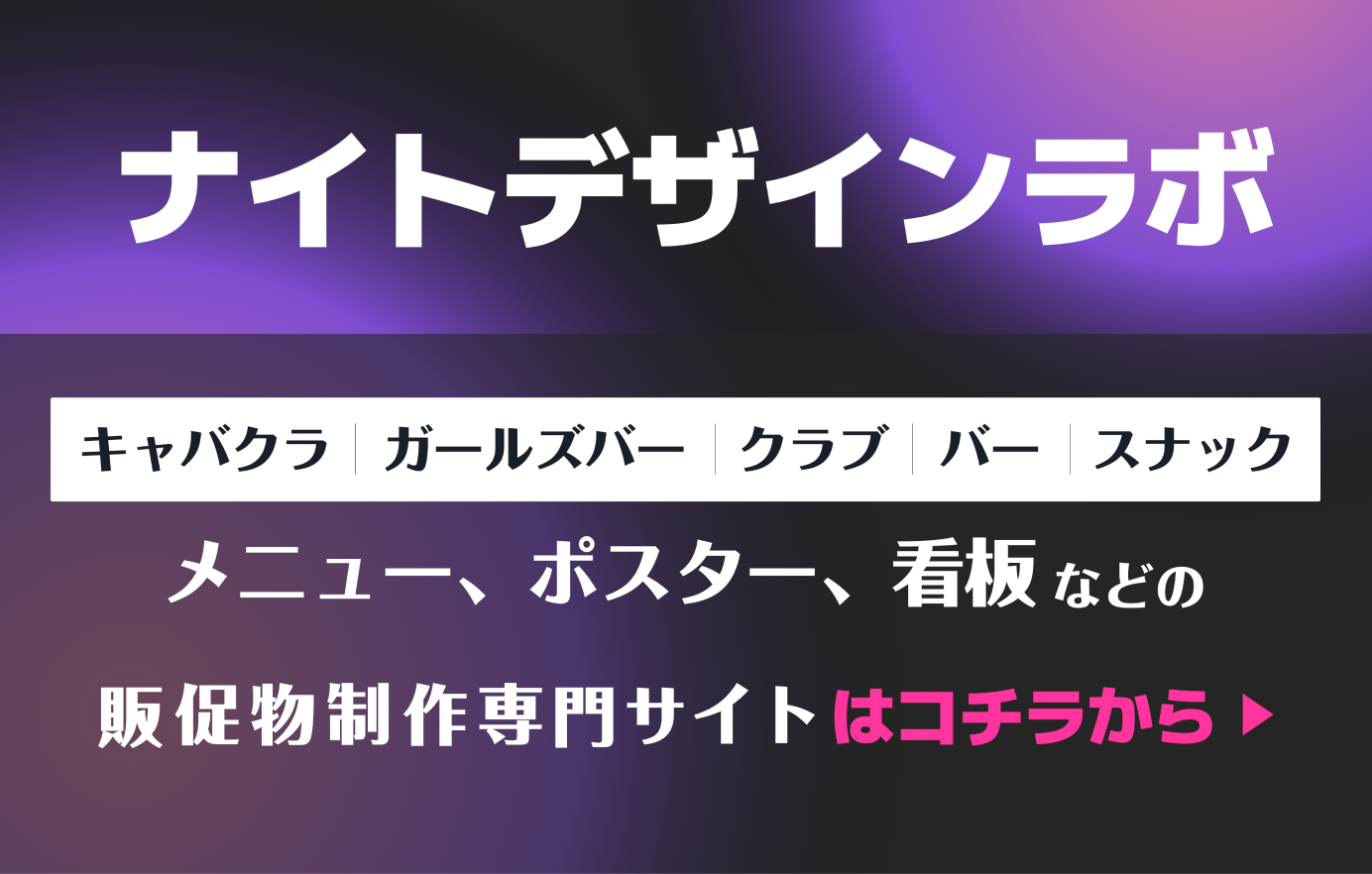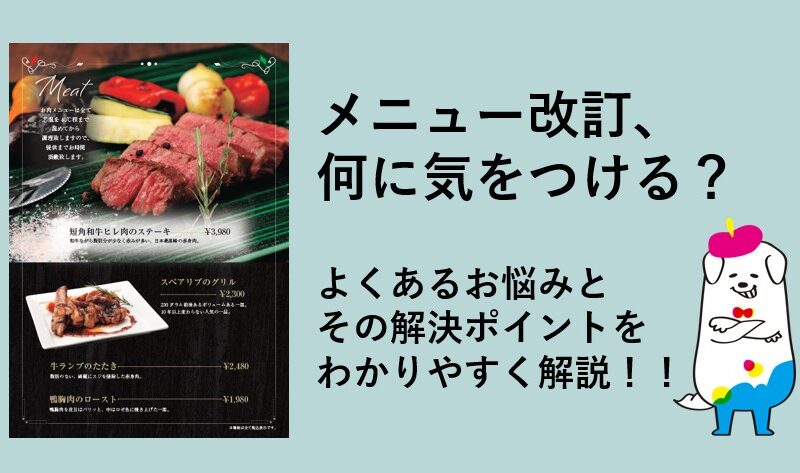
「そろそろメニューを作り直したいけど、何をどうしたらいいのかわからない…」
そんなお声をお問合せの際によくお聞きします。
メニューは単なる料理一覧ではなく、「売上をつくるツール」であり、「お店の看板」です。
今回は、メニューを作るときに気をつけたいポイントと、売りプラがお客様からご相談いただいたお悩み別の解決策をご紹介します。
目次
- 01 メニューを作るのはどんな時?
01-1 売りたいメニューが注文されない
01-2 メニューが多すぎて見にくい
01-3 メニューの雰囲気がお店と合っていない
01-4 客単価が上がらない
01-5 原価が高い料理ばかり出る
- 02 メニュー制作で気をつけたい4つの基本
02-1 「誰に」「何を」売るのかを明確に
02-2 「読まれない」前提で作る
02-3 料理の「並べ方」が売上を左右する
02-4 定期的なメニューの見直し
メニューを作るのはどんな時?
メニューを作り替えるタイミングはお店によって様々です。
原価高騰による値上げ、ありますよね。。。
メニューの見直し、必要です。
出るメニュー、出ないメニューの精査をして原価率をコントロールすることは営業する上でとても大切です。
理由は色々ありますが、今回はその中から一部の例を使ってポイントをお話したいと思います。
売りたいメニューが注文されない
お店としては「コレを食べてほしい」「これが看板メニュー」とおすすめしたいのに、
なかなかお客様からご注文いただけないということありませんか?
■ 原因として考えられることと解決策
・メニュー内で目立っていない
→目立つ位置に配置(左上/中央上)
→写真を大きく、シズル感を出す
※商品のレイアウトや、美味しそうに見える写真だけでも注文率は上がります!!
写真が暗かったり、近すぎて全体が見えないとちょっともったいないです。

・説明が弱い
→「店長のおすすめ」「一番人気」などアイコンをつける
※ちょっとしたアイコンで示すだけでも目を惹き、しっかり見てもらえます。
お店のおすすめと言われると食べたくなる心理も働きます。
メニューが多すぎて見にくい
商品数や説明文、価格やインバウンド表記など、お店として載せたい情報はたくさんあると思いますが、
それ故にお客様は読みづらいメニューになっていませんか?
■ 原因として考えられることと解決策
・情報の整理不足
→ジャンル別にカテゴリ分け
※カテゴリがわかりづらく、ゴチャゴチャして見えていると目線が上滑りしてしまい、
しっかり認識してもらえなくなります。
・写真が多すぎる
→本当に必要な写真なのか、しっかり吟味
※写真が載っているとどんな商品が出てくるか安心感はありますが、
数が多いとお客様を迷わせるだけになる可能性もあります。
メニューの雰囲気がお店と合っていない
たとえば落ち着いた雰囲気のお店なのに、カラフル過ぎたりイラストのテイストが可愛い感じだったり、と
「なんか違うな…」ということになっていませんか?
■ 原因として考えられることと解決策
・デザインが場当たり的
→店のコンセプトや内装に合わせたトーン(和風/ナチュラル/モダンなど)
→フォントや色使いを統一
※流行りのデザインを使って目を惹きたくなると思いますが、それはお店とマッチしていますか?
ここはデザインの領域ですが、お店のコンセプトやターゲットが何なのか、
せっかくのタイミングなのでもう一度見直してしっかりブランディングをすることもおすすめです。
客単価が上がらない
あと50円、あと100円単価が上がってくれれば…そんなお悩みも当然あります。
でもそれが難しい。ですが解決方法はあるんです。
■ 原因として考えられることと解決策
・サイドメニューやドリンクが埋もれている
→セットメニュー提案や、お得な組み合わせ例を掲載
→お酒やデザートを注文につなげる「おすすめ一言コメント」も効果的

お店の人はセット内容や選び方を知っているので、意外とこの部分を見落としがちだな、と思うことが多くあります。
ですがお客さんは知らないんです。
そして誰もが店員さんに声をかけられるわけではないので、わかりやすいもの、頼みやすいものを注文します。
そこで単価アップの機会損失につながってしまうこともあります。
「これをセットにするとお得なんですよ」という動線をしっかり確保することや、
「この料理にはこのお酒が合いますよ」のようなコメントが意外に効果を発揮します。
原価が高い料理ばかり出る
お店としては「あまり頼まれると正直キツい…」という商品もメニューにあると思います。
ですがそればっかり出るということも。回避したいポイントですよね。
■ 原因として考えられることと解決策
・利益率の設計が反映されていない
→高粗利商品を「おすすめ」として目立たせる
→人気の原価高商品にはオプションやセット販売でカバー
お店にとってのおすすめは2種類あります。
・原価など関係なく、本当に食べてほしい商品
・粗利率が高く頼んでもらえると利益が出る商品
上記は「客寄せ商品」として赤字覚悟で提供し、他のメニューも頼んでもらうことで利益を生みます。
”1日何食”と限定数を設けるなど、上手にバランスをとることも必要です。
また、利益率の高い商品は美味しそうな写真やお得感をアピールして、頼みやすい見せ方に。
お客様に美味しいものを提供したいのはお店として当然ですよね。
ですが経営をしなくてはいけないので、そこはしっかりお店を継続させながら、
お客様に喜んでいただく方法を考え、対策していきましょう!
メニュー制作で気をつけたい4つの基本
1. 「誰に」「何を」売るのかを明確に
→ ターゲットに合わせて構成や見せ方を変える
ファミリー層なのか、会社員なのか、年齢はいくつくらいなのかなど、お店の立地によっても変わります。
同じ地域の他のお店も見ながら、自分のお店のターゲットを明確にしておくことが大切です。
2. 「読まれない」前提で作る
→ 写真と見出しで「一瞬で伝わる」工夫と長文説明は避ける。
もちろん理想は「読んでもらうメニュー」なんです。
ですが、これは客層によって変わってきます。落ち着いて読んでもらえるお店なのか、回転率も高くにぎやかなお店なのか。
後者の場合は時間をかけずにパッと選んで注文する事が多いので、出来るだけわかりやすいメニュー作成が必要になります。
3. 料理の「並べ方」が売上を左右する
→Z型/F型の視線誘導、価格帯のグラデーション、セット提案の見せ方。

前回のブログでも触れましたが、人間の心理として、ZやFの形になるように読むというデータがあります。
それに従って、各ポイントに頼んでもらいたいメニューなどを配置するという戦略も必要になります。
4. 定期的なメニューの見直し
→ 新商品追加や価格変更に合わせて更新。年に1回の見直しが理想。
いつ来ても同じメニューではお客様も飽きてしまいます。
日替わりで人気だった商品をグランドメニューに追加したり、逆に出ていない商品を削る、
またはレイアウトを変えて目立つように配置するなど、売上や原価率の見直しを行いながら、
メニューの見直しもしていくことがおススメです。
まとめ
メニューは作って終わりではありません。
見やすさ・わかりやすさ・利益設計・注文導線…さまざまな要素が絡み合っています。
だからこそ、最初に「よくある悩み」を知っておくことが、成功の第一歩になります。
新しくメニューを作る際には、ぜひ今回のチェックポイントもふまえつつ、考えてみてください。
もちろんご連絡いただけましたら、一緒に考えてご提案いたします!
お店側の希望、お客様の希望、どちらも叶えられるメニューを一緒に作りましょう。
▶ お問合せはコチラから!
よかったらコチラの記事もご覧ください★
▶メニューのデザインポイントについてはコチラ
▶商品を魅せる撮影術についてはコチラ
ではまた次回ですっ!